「サトルボディヒーリング」シリーズ 第26回「直観の力」
今回のブログシリーズはユニティインスティチュートで開催されている
「サトルボディヒーリング」のご案内として連載しています。
http://unityinstitute.jp/subtlebody.html
今回は第四身体/チャクラをテーマに 「サトルボディ―ヒーリング」の本からの一部抜粋をご紹介します。(新装版近日発売)
https://unityinstitute.jp/mail/order_book1.cgi
今回紹介するのは第四チャクラの領域、
第四身体と関連したハートのエネルギーについてです。
直観はどこからやってくるのでしょうか?
最近は脳の研究が進み、右脳が直観をつかさどるという説が一般的なようです。
ノーベル生理学・医学賞を受賞した大脳生理学者であるロジャー スペリーは、
人間の意識は物理的な脳の機能だけからは説明できない
という結論に達しているようです。
それはともかく、私が常々脳に関連して疑問に思っているのは、
もしダーウィンの進化論のように人間の脳も進化してきたのならば、
一般の人は脳の機能の5%も使っていない、というのはおかしいのではないかと思うのです。
最近読んだ脳の研究によると、
脳は受信機としての役割をしているという説があるようです。
その研究によると、実験のマウスに学習させて、
脳の記憶の部位を破壊したにもかかわらず、
そのマウスは学習した記憶を保持していたので、
記憶は脳の中にあるのではなく、ちょうどクラウドコンピューターのように、
どこかに蓄えられていた記憶をダウンロードする受信機だという
仮説がなりたつというふうなことが書かれていました。
そのように考えると、過去生の記憶を保持している子供たちや、
人の過去生をリーディングしたり、
あるいはノストラダムスやスエーデンボルグのように
アーかシックレコードを読むことができる人たちの
予知能力などの説明もつけやすくなります。
その説によると、直観もどこかからそのようなひらめきを受信するのかもしれません。
サトルボディヒーリングでは、
その直観は、第4身体の中心の空(くう)により近いところで機能すると考えています。
それでは、 今回は第四身体/チャクラをテーマに
「サトルボディ―ヒーリング」の本からの一部抜粋をご紹介します。
………○…………○…………○………
サトルボディヒーリング 第六章より 「直観の力」
探求者が第4身体の外側の層から離れ、空(くう)の中心へと向かうにつれ、
人は人間の思考で最も理解しがたい資質のひとつ
――直感の力――に出会います。
直感について人々が戸惑うのは、それがどこから来るのかわからないからです。
直感的思考は連続した線形では移動せず、
あっと驚くような神秘的な飛躍をします。
直感的アイデアは、説明を飛ばして、
どうやら「何もないところから」湧いてくるようです。
たとえば、相対性理論の最初の啓示がアルバート・アインシュタインに
直感的な閃きとしてやってきたのは、路面電車に乗っていたときだと言われています。
そのあと初めて、彼は直感で得た閃きを証明する仕事に専念しました。
過去数十年の間に、科学者や心理学者の中に、
通常の思考は脳の左半分の機能であるのに対して、
直感的思考は右半分の機能だと主張する人たちが出てきました。
彼らの研究の有益な副産物のひとつは、
直感の機能に新たな敬意が与えられたことです。
直感による結論は証明することができないがために、
何世紀にもわたり非難を被ってきました。
「それでは意味をなさない」というのが、直感的観察力への典型的なはねつけ方です。
それでも直感的な人たちは、彼らの「予感」は、ほとんどいつも間違わないと主張します。
ちょっと考えてみてください。
これまでに、何か「予感」があってもそれを退けて
、マインドの合理的な部分が命ずるところに従うことにして、
やっぱり最初の印象がまさに正しかった
といったことがどれほどありましたか?
直感が通常の思考とどう違うのかを理解することは大切です。
通常の思考は線形に進行していきます。
ひとつの思考に別の思考が鎖のようにつづき、
問題は合理的に扱われ、いくつかの事実は
理解しやすいようにひとつにつなぎ合わされます。
直感は、第4身体の中心の空(くう)により近いところで機能します。
この空の中には、固定化した思考パターンを
薄めて和らげるだけのスペースがあります。
思考の間にギャップが現れます。
思考の鎖が切れて、
新しく創造的な思考パターンがひとりでに起こるスペースを与えます。
このようにして直感は、一見すると関係のない事実や出来事の間に、
新しく神秘的なつながりを見出すことができ、
驚くほど思いがけない結論を下すのです。


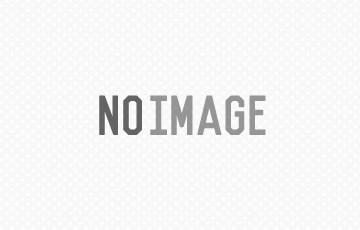


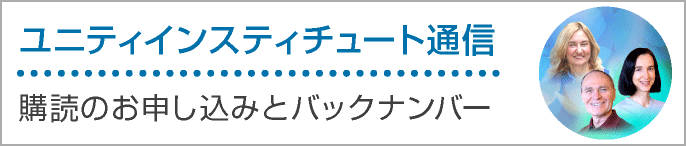
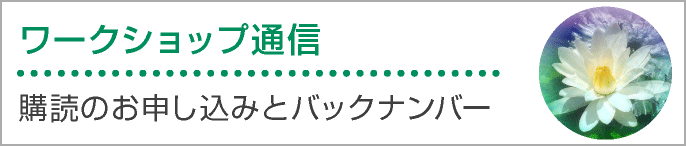
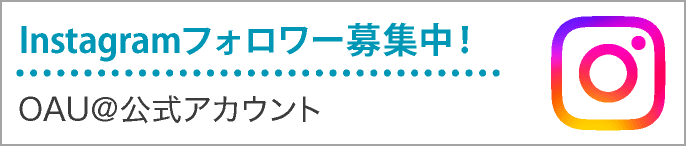
最近のコメント