なぜ「幸せの隠し球」なのか?
CCTの共同開発者トゥプテン・ジンパ博士は『コンパッション――慈悲心を持つ勇気が人生を変える』の著者の中で、コンパッション(思いやり/慈悲心)は「幸せの隠し球」だという言い方をしています。
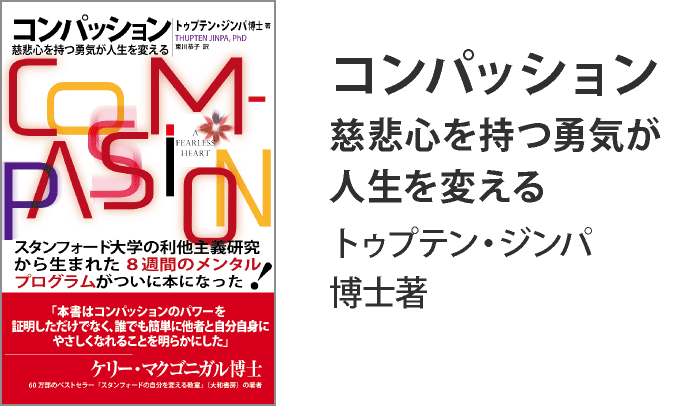
ここでいう「隠し球」とは野球の技ではなく、「幸福をもたらす秘密の切り札」というような意味です。
ダライ・ラマはこんなパッションについてこのように言っています。
「人を幸せにしたければコンパッションを実践しなさい。
自分を幸せにしたければコンパッションを実践しなさい。」
この言葉からすると、コンパッションは「隠し玉」でもなんでもなく、幸せをもたらす王道のように思えます。
なのになぜ、ジンパ博士は「隠し球」と呼んだのでしょうか?
それは、私たちが気づきにくい深い層で、様々な影響を私たちの人生にもたらしているからです。
正直に言えば、私は最初、コンパッションの瞑想やワークは、Oshoの瞑想(ハート瞑想を含む)に比べると表面的で簡易なテクニックに見えていました。
ところが、ウタ・コマラの「コンパッションに救われた」という体験や、私自身が瞑想だけではほどけなかった日常の悩みに、コンパッションの実践が具体的に効くことを体感し、考えが変わりました。
深い瞑想(Oshoや禅)の価値はもちろん疑いようはありません。
ただ、その体験が起こるまでは大きな努力や長い時間が必要だったりします。

気づきを日常の言葉や行動へ翻訳するのに苦労することがあります。
人の行動の大半は無意識に支配され、幼少期の条件づけが色濃く働いています。
瞑想が深まって、それらの無意識にも気づきをもたらすには並大抵ではなかったりもします。
しかし、このCCTのいいところはそれらの瞑想とともに、科学が融合して用いられているところです。
そうすることで、瞑想だけでは長年かかるような気づきにも、シンプルなテクニックで気付けたり、それを日常生活に実践できるようにするところまで落とし込むことができるようになります。
近年の心理学・神経科学は、この「なぜ効くのか」を少しずつ解き明かしてきました。
コンパッション実践が無意識のパターンにつながる脳と神経のメカニズムを解明し、毎日の選択を変えやすくすることが示されています。
コンパッションが「切り札」である理由
1)感情的に反射していたことに対して、応答することができるようになる。
コンパッションを鍛えると、これまで脅威を感じて、カッとなって反射していたことに対しても、落ち着いて、状況を見極める落ち着いて行動できるようになります。
これは瞑想が深まればできるようになることですが、コンパッション瞑想で神経回路が通りやすくなり、感情に飲み込まれにくく、落ち着いて選べる自分が増えます。
2)介護や人のために尽くすこと消耗するのではなく、充足を感じるようになる。
誰かの役に立てた、つながれた――と感じると、脳の報酬ネットワークが働き、「やってよかった」という温かい手応えが生まれます。そうすることで燃え尽き症候に陥ることなく、むしろ続けたくなる感覚が育つ。
3)心・体・人間関係が一緒に整う
コンパッション/ラヴィングカインドネスの実践は前向き感情を押し上げ、それが迷走神経(からだの落ち着き)を整え、さらに人とのつながり感を高めます。心・体・人間関係が同時に整う循環が起きます。
4)人間関係の土台が変わる
セルフ・コンパッションで自己批判がやわらぎ、言葉が穏やかになります。すると衝突は減り、ぶつかっても修復が早い。自己コンパッションの介入研究でも、抑うつ・不安・ストレスの低下が幅広く報告されています。
こうした働きは、ふだんは無意識のレベルで起きています。
そして、この無意識のメカニズムに意識的にアクセスし、だれでも再現可能にしたのが、スタンフォード大学のCCT(コンパッション育成トレーニング)です。CCTを生んだCCARE(共感と利他主義の研究所)は、まさにこれらの仕組みを研究していました。
セルフ・コンパッション(内なる批評家をやわらげる)
共通の人間性(私も相手も同じ人間だと想い出す)
感情が高ぶる前に気づいて戻れる。
コンパッションは、難しい場面で賢く応答するための、心と脳の使い方です。
CCT入門は、その秘密の切り札を誰にでも回せるようにするための実践クラスです。

https://oshoartunity.com/blog/post_lp/cct_introduction2025_09
OAU
えたに















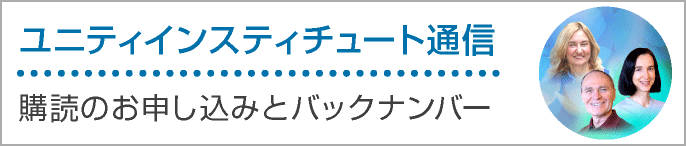
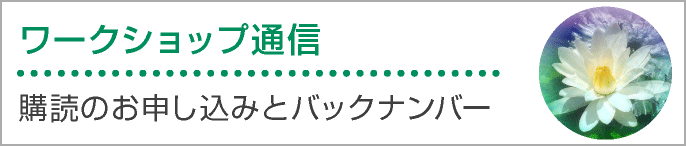
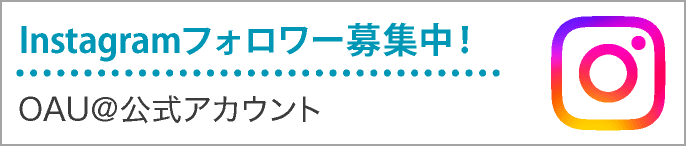
最近のコメント